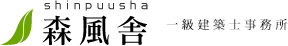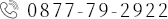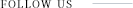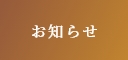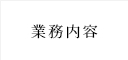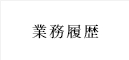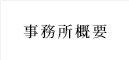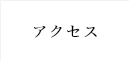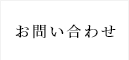2011/03/18 散歩道
中国武術を取り入れた健康教室開催のご案内
この度、長男増田浩一が近くの公民館をお借りして、
健康教室を開催することになりました。
春から開催の予定で、
中国武術の経験を生かし、だれでも簡単にできる運動プログラムを考えています。
参加費は無料となっていますのでお気軽にお申し込みください。
ただし、施設の使用上まんのう町民に限らせていただきます。
2011/01/14 散歩道
リフォームに補助金がつく
1995年1月17日は阪神淡路大震災に見舞われた日である。
6000名を越える死者を出したこの災害から16年、
約5600人が木造家屋の倒壊や家具の転倒などで命を落としている。
1月17日は深く記憶にとどめ、それを呼び起こし、日常を振り返る日である。
昨日の新聞にも報道されたが、
香川県は1981年6月までに建築された住宅に対し、耐震改修工事をした世帯に
30万円の補助が受けられる制度を始めた。
リフォームを考えている人は、構造的な耐震診断を含めて、この機会にしっかりと
家の骨組をチェックしてはいかが。
南海地震が取りざたされ、日本全国どこで地震がおきてもおかしくない今日、
住まいに命を奪われない状態にしておくことが大切です。
申し込みは3月15日まで(県住宅課087-832-3584)
2010/12/15 散歩道
テレビがない!?
今年の正月はくたびれたテレビ(まともに画像が出ない)をほっぽり出して「チデジ」とやらに早く替えろとやかましく言っているので、ぼくもそろそろ替えとかんなあかんという気にさせられてしまって、ごひいきの電気屋さんに「テレビお願いします」と言って更新をお願いした。
電気屋さん、カタログを持ってきてくれて「今テレビがありません、いつ入るかもわかりません、コレコレだとなんとか・・・」ええ!!なんとテレビが ない!!さてこんなことは今までになかったはずだ。聞くとエコポイントやらで需要が供給を大幅に上回っているらしい。ちまたの量販店が買い占めているので はないか・・・なんてかんぐってしまう。アナログ放送修了のメッセージとエコポイントで需要が沸騰してるみたいだ。こんな時期に、と考えなおしてみるがく たびれたテレビは邪魔だし、このさい思いたったら吉日、パナソニックでなくたってかまわない、スリーダイヤだって負けてはいない。「ある分をもってきてく ださい。」
と、いうことでわが家のリビングには16年ぶりに新しいテレビがやってきた。
ないと言えば、
「断熱材がない」今動いている現場で設計スペックの断熱材が「ない」と現場監督から電話が入った。ええ!断熱材も・・・。新建ハウジングによると「昨年 2009年4月の改正省エネ法をはじめ、6月の長期優良住宅法施行、今年2月からのフラット35Sの金利引き下げ拡大、3月のエコポイント制導入など、住 宅の省エネ化を促進する制度が充実し、ここにきて新築の次世代エネ規準適合の割合が増えたことがある。」と書かれている。納期が2ヵ月も先になるっ て・・・そんなんだったら工期に間に合わないし、工事が滞ってしまう。「代替品でいくしかないな」・・・監督に指示を出した。
さて、テレビにしても断熱材にしてもこれらが、省エネ化に役立つかどうかはよく考えてみる必要があると思うのだが、ある一定の方向が示されると盲目 的に突き進んでいく国民性がよく出ている現象である。なんらかの制度規準が定められると、そこには利潤のネタが内在しており今はさしずめ、家電業界と断熱 建材といったところか。この制度で国民生活は豊かになり、はたまたこれからよくなるのであろうか。
2010/11/05 散歩道
木の第一線
山の木は使ってなんぼの世界である。
植えて大きくなっても使われなくてはなんにもならない。
先人が植え、世代をつないできた木は孫の代でやっと使えるまでに育つ。
人知れず山深く静かに大きくなった木は里に送る水を涵養してきた。
やっと日の目をみるときがやってきた。
チェンソーが唸り、いく年月を経た木が伐られていく。
植物としての木のいのちはここで絶たれた。
木はまた新たな場所でいのちを得る。

山深く分け入っていくとチェンソーの音が聞こえてくる。
進むにつれてしだいに大きくなる。
伐られた木が架線で集材されていた。
2010/08/17 散歩道
既存建物詳細調査
8月16日(月)お盆の最終日、
高松のT邸において昭和37年に建てられた木造住宅の詳細な調査が行われまた。
(有)MOK-MSD、岐阜県立森林文化アカデミー、住宅医スクール、香川大学、
かがわ木造塾による合同調査です。
これはかがわ木造塾のDさんの関係の仕事で、
同塾講師の三澤文子さんが実施されている建築病理学に基くもの。
既存住宅を長く使っていくため、国土交通省長期有料住宅先導事業による、
住宅改修システムの位置付けとなっています。
調査内容は、住まい手のヒヤリング、室内環境、床下、小屋裏、2階床、
地盤調査、構造、既存図面作成、温熱環境、設備・・・と多岐に渡り、
詳しい調査を行うことで、建物の現状を把握し、
どのような改修をすれば良いかを検証してゆきます。
未明に岐阜を発ち来県された学生さんたち、彼らの若いエネルギーには脱帽。
19名の参加の中でこの調査は行われました。
調査の手順や手法について、
たしたちは協働参加することで貴重な体験をさせていただきました。
住宅改修は既存住宅のストックを生かし、安全快適に住み継ぐことに他なりません。

屋内の地盤調査の様子。
手動式の管入試験です。
打撃力と進入度の相関関係によりデータが得られるそうです。

天井裏の様子。
間仕切りの土壁が天井裏で止まっています。