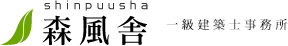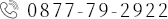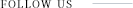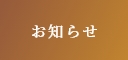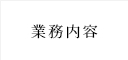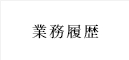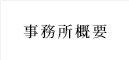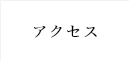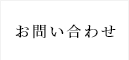2022.02.23 建築
板塀のコト/隣地からも美しく

板塀の納まりを考えるとき、支持をどうするか。金属の支柱で足元をコンクリートに埋め込んで固定するのが一般的だが、全て木で納めたい時はバットレスを付けるというのが古来のやり方で、これだと片方に出っ張りが生じる。それも嫌だなあって思っていたら、道すがら目に留まったのがこの大和塀で、スッキリと設えている。支持の角材を等間隔に置いて、基礎のコンクリートと塀の木支柱をステンボルトで縫い付けている。これだと出っ張りがないから、表裏関係なく取り付けることができる。ただコンクリート基礎の立上りは必要だが。オール木なので経年変化による木の風情が楽しめて、年数を経てもう終りかなって時は土に還り環境負荷が少ない。この板塀、とある製材・材木店の塀で、敷地内には商品の木材が整然と積まれていた。
2022.02.20 住宅
床材について/スリッパは要らない

日々の暮らしの中で一番人の肌と触れるのが床だと思います。ぼくは知識が乏かった若い頃、木質の床板と言えばWPC加工された表面に薄い松などのヘギ材が貼られている合板系のものを使っていました。この建材は木に似せたプラスチックと言っていう代物で、木の特質である吸湿性が無くて夏場に歩くと不快きわまりなくスリッパが必要でした。今は特別の事情がない限りは使いません。写真は熱圧加工したスギ30mmの厚板にリメイクした住宅で、素足の歩行感がすこぶる足にやさしい一押しの材料です。柔らかいのでキズはつきやすいですが時の経過と共に気にならなくなります。また少し固めの質感を求めるのであれば、ヒノキやカラマツが良いでしょう。地マツは固く水にも強いので捨てがたいですが、今はちょっと手に入りにくい。いずれにしても工業的な加工を施さない無垢材です。日本にたくさんあるスギやヒノキを使ってお家をつくることで、日本の山(自然)を守り生活の質(QOL)を豊かにしてくれます。
2022.02.19 建築
数十年を経た床下を見ると

構造体は健全に保たれていました。まずは安心。ここのところの建物調査で普段は目にすることのない床下や天井裏を点検することで、建築当時の様子を伺い知ることができて興味深いものがあります。コンクリート基礎や下地の木材は劣化もなく良好ですが、建築当時の清掃は不十分だったようですね。カンナくずやノコくずをとらないまま床を伏せ込んだようです。今は床下環境を活かす造りもあって工事の残渣がある状態での引渡はあり得ません。いつの時代も良質な仕事は見えないところを大切にします。
2022.02.11 Project
じいちゃんが植えた木の家P②/ごあいさつ

まずはヒノキの森で眠るじいちゃんとばあちゃんにごあいさつをするためにヒノキの森に登りました。ここでは二人が寄り添ってこの森を見守ってくれています。ここの森は昔桃畑であったところで、僕が子供の頃はよく手伝いをさせられており、桃の栽培をやめてからじいちゃん(父)がヒノキを植えました。たぶん将来木が大きくなったら何かに利用できると考えていたのでしょう。僕が林業に興味を持ったのもせっかく植えてくれた木だからなんとかしなければ、と思ったのが動機の一つです。それに建築設計の仕事をしているからこの木を活かさない手はありません。まあ昔の山里では当たり前に行われていた自分で育てた木で家を建てることをやってみたいと思います。
2022.02.02 建築
地域木材活用セミナーを終えて
2022年1月26日にNPO法人サウンドウッズの安田さんを招請して、香川県主催による「地域産木材を活用した公共建築物をつくる」と題してセミナーを開催した。当初は26日と27日の2日に渡り、一日目が講演、二日目が現地見学の予定であったが、オミクロン株のまん延のため急遽オンライン開催になり一日に集約しての実施であった。以前だったら中止又は延期というはめになったであろうが、昨今のオンラインによる手段を得てからはこうして開催ができる。これはこれで悪くはないし経験値を重ねることができる。さて、安田さんの講演は2時間以上に渡り濃密なもので、林業から建築に至るまで豊富な実績事例を示しながら木材の有用性を熱く語つてもらい、地域材を使った木造建築をつくる上で木材コーディネータという職能が必要であることを示していただいた。2000年代初頭が地域材材用の黎明期だとすれば、あれから20年を経た今は全国で造られる木造建築が活況を呈し、拡大利用期に入っているのはまちがいない。香川においても例外ではなく、今後それぞれの場所で木の建築がつくられていくであろう。これから香川の木を使って香川らしい建物がたくさん生まれることを願っている。そのためには川上~川中~川下のポジションが連携を欠かすことなく、お互いを理解し、木材をコーディネートするシステムの組み立てが必要である。