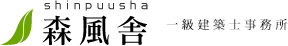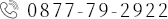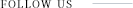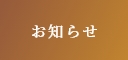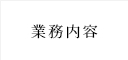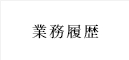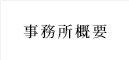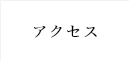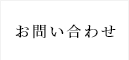2012.01.30 住宅
縁の下の力もち
文字どおり、これは縁の下。
ほこりっぽい。
昔の家屋の縁の下は土のまま地面が現れている。
通気の状態がよいので完全に乾いた状態だ。
耐震改修のため
縁の下の状態をみるためもぐってほふく前進で這い回った。
これはきついね・・・・
ここで補強工事をしてくれる職人さんには頭が下がる。
今の住宅の床下空間は狭い。
昔は床下を掘り下げるなどして後々のメンテナンスのために備えたが、
今は人が這って移動できるギリギリの高さだ・・・とても作業なんてできない。
束は古材を再利用している。
昔の人は木を大事に使ったんだ。

縁の下は妙にパワースポットの空間だ。
床下をどうつくるかをもう少し真剣に考えなければならないね。
2012.01.22 散歩道
土壁は究極のエコ建材
土壁は究極のエコ建材。「土壁はさぬきのうどんである」と言った人がいる。身近にあるとあたりまえだが、県外に出てうどんを食べると、さぬきうどんのうまさがよくわかる。経験と技で練られたさぬきの手打ちうどんは格段にうまいのである。
土壁が使われる家づくりは、全国的にみるとかなり減っているが、香川はまだまだつくられている。土壁の家がつくられるには、それを求める住まい手が いること、壁土となる良質の土があること、壁土をつくる業者さんと土壁をつくる職方の人たちがいることの三点が上げられ、どれが欠けても土壁は衰退する。 また、夏の蒸し暑い瀬戸内の気候が、吸湿性に優れている土壁を求めているといえよう。
昔、親が建てた家づくりを思い出す。今のようにハウスビルダーによる家づくりが一般的になる前の話。製材所、大工、左官、屋根屋、板金屋、電気屋、 建具屋、と主な職種の人たちを直接雇うかたちで家づくりは進められた。元祖直営方式だ。基礎づくりは父親が中心になり大工さんを手伝い、材木は地元の製材 所で山から降ろした木を製材して手当した。製材所で刻まれた材木は現場に運ばれて組まれる。棟上げの日は近所の人たちが「手間換え」で手伝いに来てくれ た。今で言えば自治会の小イベントみたいなもので男衆は現場、女衆は台所を手伝った。
人が多いから、みんなできることを次ぎ次ぎにやり、貫を入れ壁小舞まで一日でほぼ終えてしまう。素人がやるのでアバウトな面も多く、おおらかな家づ くりである。今のように耐力壁がどうの、小舞の割付がどうした、土の強度はあるのかなどと細かいことは言わない。全てが経験則の世界。小舞竹は近くに生え ているものを切り、(この頃はどの家の屋敷にも小舞用の竹があった)専用の器具で竹を割るのは子供の仕事である。元をこれにあてがい、割れ目をつけて竹を 持って走り割っていく。子供といえども家づくりの一役を担う。大人が現場を計って切り合わせ、運ばれた竹は数人の手で編みつけられて、あっという間に家の かたちがみえてくる。竹は生だったが、土壁の乾燥にたっぷり時間をとるので、土といっしょに自然に乾いたのだろう。足掛け二日で小舞は組あがり、これから 土付けとなる。
壁土は左官さんが段取りして現場に入った。たぶん土屋さんから仕入れたのだろう。それに近所の農家で分けてもらったスサの稲藁を切り込み、水あわせ と数回の切り返しで土とスサが馴染むのを待った。やがて程よく粘りが出てくる。荒壁付けは大直しを含めて父の仕事である。子供には壁土を差し出す仕事が回 され、塗り手と呼吸がかみ合って、その場の空気感が心地よい。左官さんの出番は中塗りからで、このように小舞掻き、荒壁付けまで自分たちでしていた。今は 「住まい手と共につくり・・・」などと言っているが、かつては住まい手自信で相当部分をつくるのが普通であったのだ。スローライフなどおしゃれな言葉は聞 かなかったが、時間の流れがとてもスローだった。

2012.01.14 住宅
耐震改修始まる
昨年実施した耐震診断にもとづいてS邸の耐震改修の工事が始まりました。
まずは2階から、
天井と一部内装を取っ払い、補強工事の準備かに入ります。
この耐震改修工事は60万円の補助金が出ます。

小屋組は合掌で木の状態は健全です。
小屋裏換気口がみえ防虫網もちゃと張られています。
ボルトなどの金物が木の痩せもあって緩んでいるため締め直します。
2012.01.02 散歩道
今年もよろしくお願いします
新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
山と暮らしを見つめ地域の木を使った住まいづくりや建築を、
原点に立ち返りがんばります。
毎年登っている城山は2日が初登りになりました。
故郷の里山はいつもと同じように静かにたたずんでぼくを迎えてくれます。
当たり前に暮らすことの日常が続くことを願っています。
今年一年よい年でありますように。

2011.12.08 住宅