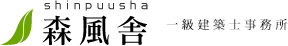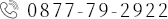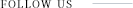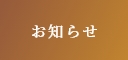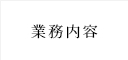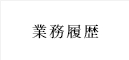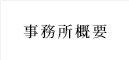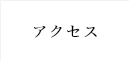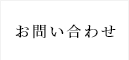2011.10.06 住宅
風呂の改修2
この様子なら案外工事が終わるのが早いかも知れない。
既存の撤去後三日目で浴槽が据わった。
前は青だったが今度は白にした。最近は色を決めることに迷わなくなり、特別に意図するところ以外は白でいく。昔はあれこれと色決めに迷っていたが、最近はで迷うことがない。
色きめの規準は、
使う材料を限定し、素材そのものがもっている色を生かすことに決めたため迷う必要がなくなったわけだ。
やはり時代のながれで、このような薪風呂は「絶滅危惧種」的なものか、風呂がつける職人(左官職)は少ないようだ。でもこれからはまたこのようなスローなライフスタイルが見直されるのではないかと、
ぼくは思っている。

築炉ユニットを設置しているところ。
昔はこういうのはなく、左官さんは経験と勘で耐火煉瓦をついていた。

浴槽が据わりました。

立上のレンガも積み終わり、あとは仕上げになります。
2011.10.03 住宅
風呂の改修1
辛抱を重ね重ねて、だましだまし使ってきたがとうとう限界がきた。
割れたタイルはテープで押さえ、水が漏れる入り隅のシーリングの補修ももたなくなり、やっと重い腰を上げて風呂を直すことにした。
こだわって薪の直焚きの風呂釜を今回も据える。築後18年だ、よくもったとも言えるし18年しかもたなかったとも思うが、毎日けっこうハードに使う場所だからこんなもんだろう。
建築の部位は長く使っていると設計や工法に弱点が見えてくるものだ。新築のときは以外と見栄えもよいのだが、いったん壊れだすともうたいへんだ、そこらへんがデザインのしろころなのだが、意外とそのときは気がつかないこともある。
いっそのこと、ユニットバスにという考えは今回の改修においても論外だった。お金の面からも、工期の面からもその方が安いかも知れないが・・・
しかし「薪で風呂を焚く」というこだわりがある。なにしろ燃料はタダで調達可能だし、その行為に執着をもっている。
と言うわけでわが家の風呂のリフォームが始まった。ざっと一週間の工期だろう。その間は一つ前の古い風呂がまだ存在しているからそれでなんとかしのげる。

風呂釜と炉部分の耐火煉瓦がのいた。

もとあった場所に新しい釜が据わる。今度は少し大きい。
2011.09.22 散歩道
備えの本気度
東南海地震がとりだされる今日、当地香川にあっては備えに対する県民の意識はいまひとつの気がする。先般も当会(フォレスターズかがわ)の大西氏と、東日 本大震災の派遣活動に従事した陸上自衛隊第14旅団の楠見氏の講演がまんのう町町民文化ホールであった。まんのう町老人クラブ仲南支部とまんのう町教育委 員会によるものだったが、聴衆のほとんどがお年寄りであった。私も大西氏の前座で耐震診断と耐震改修について、香川県の取り組みを少し話をさせてもらっ た。住宅の耐震診断に6万円、耐震改修に60万円の補助が付くことを説明したが、はたしてどれだけ意識啓発になったかどうか・・・。自然災害は明日は来な いかもしれない。明日来るかもしれない。科学的にある程度予知はできても絶対的なものではない。さて、この補助金がもらえるには前提条件がある。「昭和 56年5月31日」以前に建てられたもの」とある。いわゆる新耐震といわれ建築基準法が改正された日を規準に線引きをしているわけだ。はたしてこれは意味 のあることなのだろうか?実務に携わってきた者としては、それ以降の住宅は耐震性が担保されているとはとても思えない。ましてや地方の確認申請のいらない (確認申請が安全を担保するものではないが)地域においてはそのような線引きは意味をなさない気がする。基準日なんか設定せずに、危ないと思える住宅は全 てカバーするくらいの度量が行政にはほしい。机上の前提条件ほど曖昧であてにならないものはない。一度震災に見舞われればそんなチョコザイなものは全て 吹っ飛んでしまう。必要なのはマクロ的な視点をもって対処することである。その方が結局は「安くつく」。暮らしの器は構造的に安心して住める住宅がすぐれ てデザインもいい。
2011.08.11 建築
地元でとれたヒノキ板を張る
地元まんのう産のヒノキ板を腰壁に張りました。
スギとヒノキどちらが好きかと聞かれればどちらも好きです。
スギは柔らかくて包容力があり、ヒノキは凛として自分を主張する。
例えるなら、スギはお母さん、ヒノキはお父さんといったところでしょうか。

張られた腰板です。
15mm厚、働き巾135mm となっています。
2011.07.26 住宅